平家隆盛の礎を築いた平忠盛は58歳で世を去り、妻の宗子は、重仁親王の乳母という立場にありながら、即日出家を遂げ、以後、池禅尼 と呼ばれるようになります。
宗子の生年は未詳のため、この時の正確な年齢はわかりませんが、1140年生まれの重仁親王の乳母ですから、これが授乳を伴うものだとすると、その当時、30代半ば位と見るのが限界でしょうか。
それ以前に、二人の男子も誕生していますから、1123年頃に20歳位で家盛を、1131年に28歳位で頼盛を、1139年頃に36歳位で女子を(後世に名前が残っていないので女子と仮定)それぞれ出産したとして、ひとまず、およそ50歳位と想定しておきましょう。(ちなみに清盛は36歳)
さて、忠盛に続き、翌久寿元年(1154)に、宗子の従兄妹で、鳥羽院無双の寵臣と謳われた 藤原家成 も亡くなり、何か一つの時代の終りを感じさせるような寂寥感の漂う中、翌久寿2年には、かねてより病がちであった 近衛天皇 が、ついに17歳の若さで亡くなり、政局は一気に緊張の度を深めます。
皇嗣誕生を見ない間の崩御に、後継者問題は難航を極め、最有力と目された重仁親王も、その父崇徳院の院政開始を懸念する美福門院によって退けられ、紛糾の末、図らずも、崇徳院の弟 雅仁親王(後白河) が皇位に就くことになります。
加えて、皇太子には、やはり美福門院の猶子となっていた雅仁の王子 守仁 が擁立されたことから、急転直下、重仁親王の皇位継承は、ほぼ絶望的となりました。
これまで丹精こめて養育に努めてきた皇子の事実上の失脚は、宗子にとっても心痛の極みながら、そもそも乳母となった経緯が美福門院の意によるものだとすれば、これも十分予想しうる範囲の出来事であり、無念に思いつつも、乳母の務めとして、日々の暮らしの扶助だけは続け、せめて、和歌をよく詠む父崇徳院のように、風雅の道に生きてくれれば……と、切に願っていたのではないでしょうか。
しかし、そんな宗子の思いに反して、崇徳・重仁父子の周囲には、どす黒い策謀が張り巡らされ、鳥羽法皇崩御を契機として、未曾有の争乱に、否応なく巻き込まれることになります。
「崇徳院と左大臣頼長が謀反!」
その知らせを受けた宗子は、恐れていた事態が現実となったことに愕然としつつも、平家一門のとるべき道に、思いをめぐらします。
政争に巻き込まれることを恐れ、あえて、両陣営から距離を置いてきた清盛は、依然として、天皇方・上皇方のどちらにつくか旗色を鮮明にはせず、情勢を伺うことに終始していましたが、そこには、重仁親王の乳母という宗子の立場への配慮も、多少あったのかもしれません。
源氏が既に 為義=上皇方・義朝=天皇方 と二手に別れた現状では、平家がどちらにつくかで、「勝敗の行方が決まる」と言っても過言ではありませんでした。
宗子も心情的には、「上皇方へ」との思いが強かったでしょう。
しかし、事態を冷静に客観視すれば、理由の如何を問わず、天皇に弓を引くなど暴挙以外の何物でもありません。それは相手がたとえ「上皇」であろうと、何ら変わりなく、「そのような無謀がまかり通るはずがない」と考えるのが貴族社会の常識であり、宗子とて例外ではありませんでした。
何より「朝敵」の汚名を蒙るようなことになっては、生前、身を粉にして武門平家の地位向上に努めてきた、亡き夫忠盛に申し訳が立たない……。
重仁親王の乳母であることよりも、平忠盛の妻、平家の家刀自としての立場を選ばざるをえなかった宗子には、家門存続こそ第一、ここで、情に流されるわけにはいきませんでした。
宗子の決断を頼盛より伝え聞いた清盛は、これを待ちかねたように腰を上げ、全軍を率い「天皇方」に加わることになります。
予想どおり、平家の参戦により圧倒的優位を確保した天皇方が圧勝を納め、崇徳院・重仁親王父子は、哀れな虜囚になり果てます。
その後、崇徳院は讃岐へ流され、重仁親王は出家と引換に助命され仁和寺に入室となりますが、23歳という若さで早世したといわれ、恐らく宗子は、乳母としての務めを放棄することなく、その最期の時まで、影ながら扶助を続けたものと思われます。
そこには、一抹の後ろめたさ―― たとえ、周りの人間全てを敵に回しても、皇子を守り抜くべきではなかったか―― との後悔の念もあったことでしょう。
そして、それゆえに、次なる岐路に立った時には、「清盛との対立も辞さぬ!」との覚悟を決めることになるのでした。
先の保元の乱からわずか3年余で、再び洛中が戦場と化した 平治の乱。
平家が無事勝利を収めた一方で、源氏は一族郎党が散り散りとなって逃亡を図りますが、棟梁の義朝はだまし討ちに遭った末に非業の死を遂げ、嫡子 頼朝 は捕えられて、六波羅へと引き立てられます。
当時14歳の頼朝に同情した池禅尼が、絶食してまで、清盛に助命を求めた話は、つとに有名ですが、この時のキーワードとなった「亡き家盛に似ている」との証言については、その実否を断言できるものは何もありません。あるいは、これも『平治物語』の中での虚構に過ぎないのか……。
ただ、世間の目からすると、そうした理由づけでもをしなければ、清盛の継母が捕虜の助命に動くなど、到底理解のできない、奇異なものに映ったのかもしれません。
しかし、忠盛後室 池禅尼 としては奇異なことでも、彼女が 藤原宗兼の娘 であることを思い返せば、そこに連なる人間関係と共に、もう一つの彼女の立場も見えてきます。
頼朝の母は熱田大宮司藤原季範の娘で、母親本人は既に他界していたものの、その姉妹には、 元待賢門院女房 で、今は 上西門院 に仕える者もいました。
待賢門院は崇徳院の母であると同時に、後白河院・上西門院の母でもあり、かつて待賢門院に仕えた者の多くは、彼らを主に替えながら勢力保持に努め、その団結力には、なお揺ぎ無いものがありました。
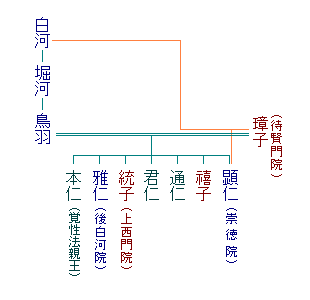 |
その 旧待賢門院派 ともいうべき面々が、頼朝の伯母(叔母)達の必死の嘆願に心を動かされ、助命運動を展開したとすると、待賢門院の伺候者であった宗兼の娘にして、官軍の総帥平清盛の継母である 池禅尼=宗子 に真っ先に助力を仰いだことでしょう。
保元の乱については、事実上「崇徳」vs「後白河」という、同じ母を持つ兄弟の争いとなったため、宗子の重仁親王への一種の裏切りにも似た行為にも、表立って非難の声が上がることはなく、むしろ、乱後の平家の家格上昇と共に、彼女を頼りにする気運が、いっそう盛り上がったとしても不思議ではありませんでした。
そして、頼りにされれば、それに答えたいと思うのが人の性――。ましてや、右兵衛佐の職にあった頼朝を恐らく見知っていたであろう上西門院本人からも、内々に尽力を要請されるようなことでもあれば、さすがに宗子もこれを拒むことはできなかったでしょう。
結論を言えば「頼朝は伊豆国配流となった」―― これが歴史上に残された唯一の事実であり、そこに至るまでの経緯は、所詮、推測の域を出ません。
ただ“火のない所に煙は立たず……”とも言いますから、このような逸話があること自体、「池禅尼殿であれば、それぐらいのことはなさるであろう…」と、誰もが納得するような、「聡明」かつ「気丈」な女性であったと見る分には、何ら異論はないように思われます。
|
|
|
|
